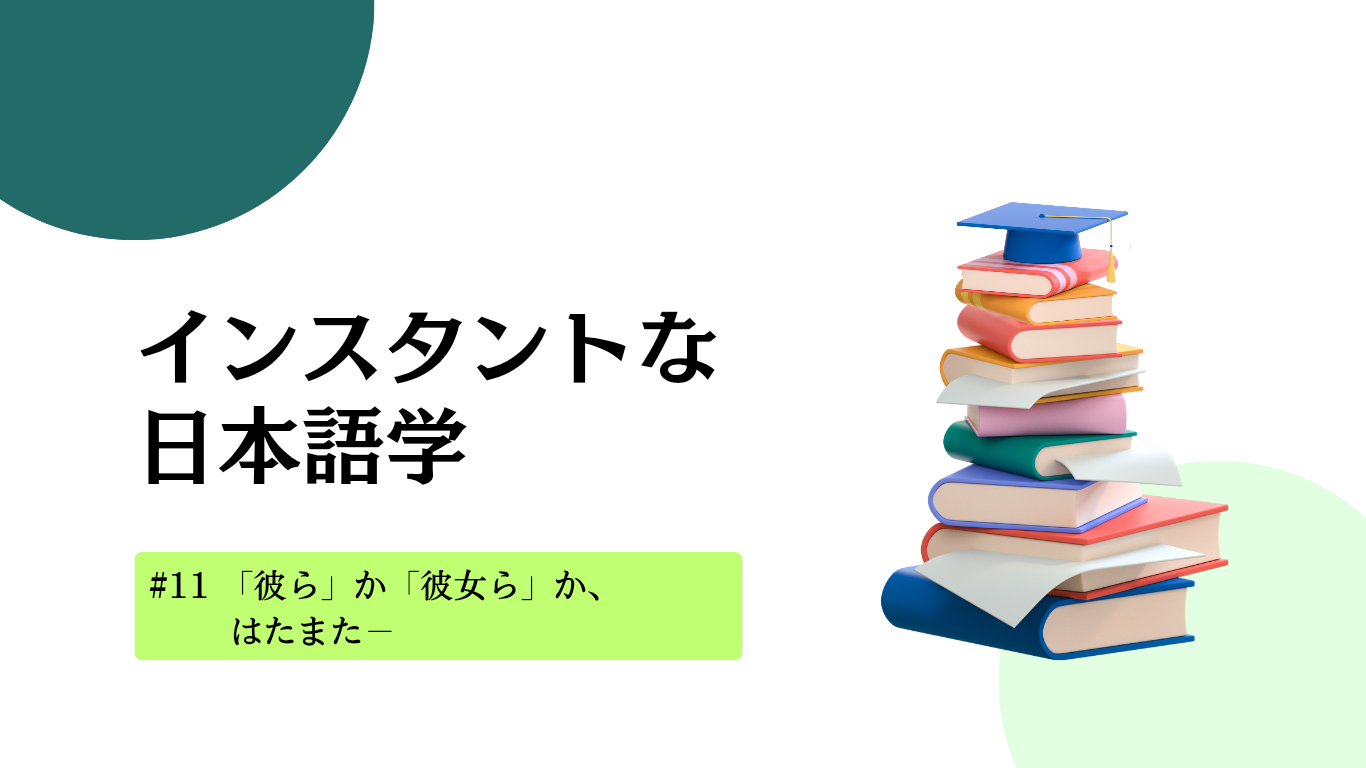
性別・収入・人種などの属性に関わらず,様々な人を公平に扱う社会のあり方が世界中で模索され続けています。日本も例外ではありません。そうした社会を私も望んでいますが,先はまだまだ長そうです。
そして,ことばにもこうした問題が現れています。例えば,「僕」「私」「彼」のような人称表現とジェンダーです。
LGBTQ+の方々をどう呼称するか
「LGBTQ+」という用語は,一昔前よりも認知度が上がったように感じます。しかし,LGBTQ+の方々を取り巻く問題は,まだまだ山積みです。
人称もその一つではないかと思っています。
私は先ほど「LGBTQ+の方々」と書きましたが,わざわざこう書いたのは「彼ら」「彼女ら」「彼ら彼女ら」という呼び方では上手く言い表せないと考えたからです。
以前,うちの学生に教えてもらったのですが,英語では「They」から派生して,LGBTQ+の方々を表す「Zhey」という表現が作られました。
日本語でもそうした表現が生まれるかというと,なかなか難しいように思います。なぜなら,英語の「They」は男性にも女性にも使えるため,文字や音を少し変えるだけでいいのですが,日本語は「彼ら」「彼女ら」のように性別によって専用の表現があります。
そのため,LGBTQ+の方々を指す表現を作るには一から作る必要があり,時間と労力がかかると考えられます。
ちなみに,中国語でも「彼ら/彼女ら」は「他們/她們」と使い分けますが,発音は同じ「tā men(ㄊㄚ ㄇㄣ)」であり,文字上の区別はあっても,発音上の区別はありません。
そのため,中国語はLGBTQ+の方々を指す人称が,比較的生み出されやすいかもしれません。(もしかしたら,既にあるのかもしれませんが)
※先日,学生たちに聞いたところ,「他們」でも「彼女たち」を表すことができるようです。
社会の写し鏡としてのことば
ことばは,社会の動きに並行して変化していくものです。例えば,昔は「貴様」や「お前」は敬語でしたが,今では相手を卑下する失礼なことばへと変化しました。それは,時代によって私たちの認識が変わったからです。
そうすると,ことばは社会の写し鏡のようなものだといえます。日本のジェンダー指数は世界的にかなり低いことで有名ですが,日本社会全体のジェンダーに対する認識が変わったとき,私たちのことばはどのように変わるのでしょうか。
