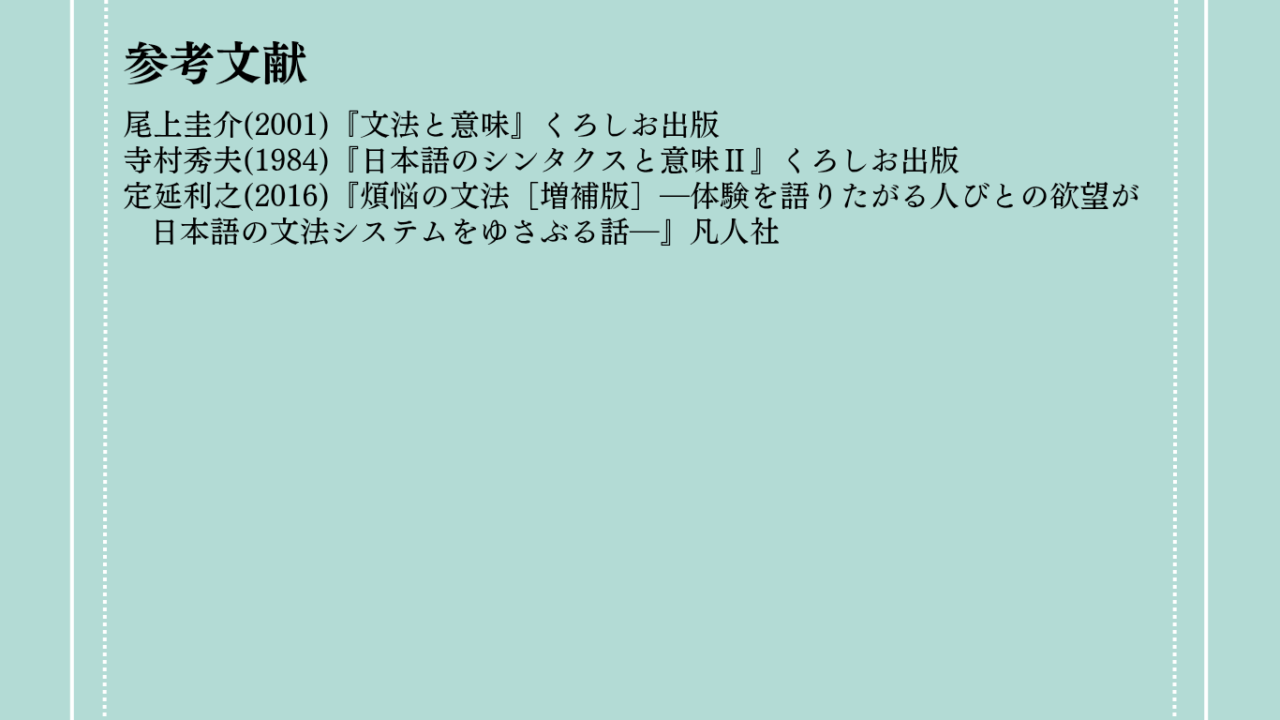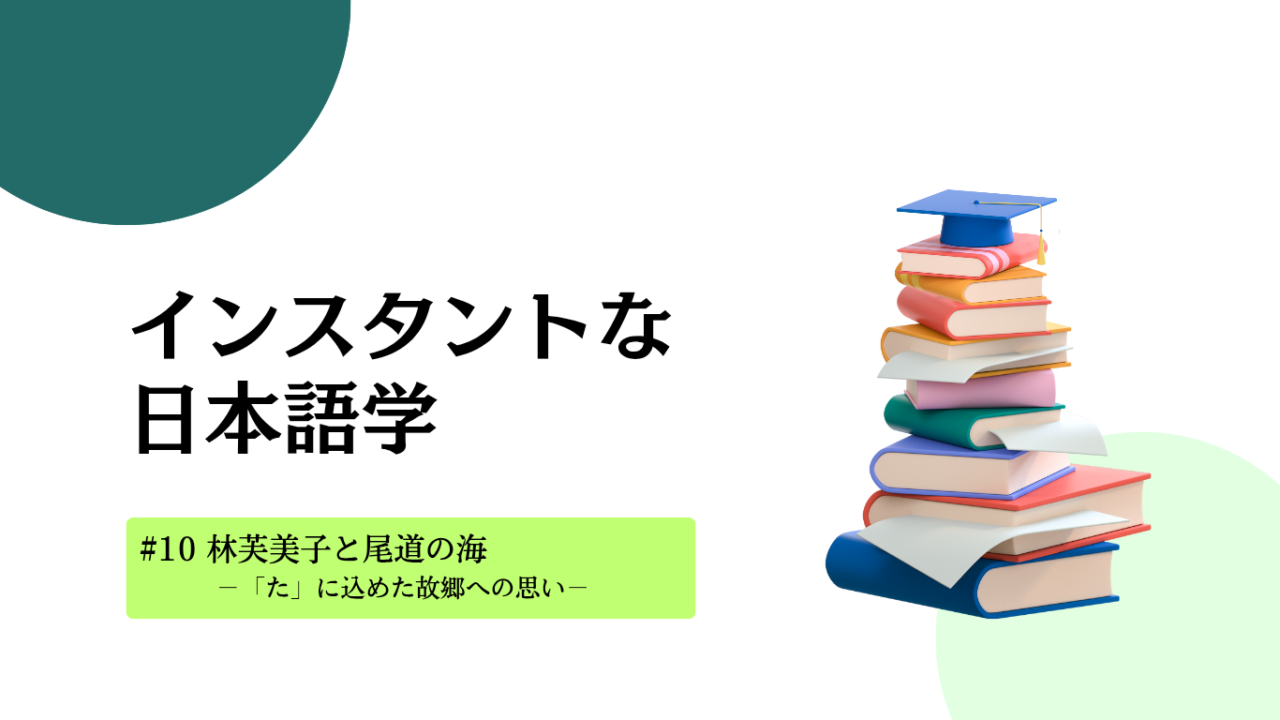
先日,出張で尾道へ行ってきました。ノスタルジックを感じる,好きな場所の一つです。
尾道駅から少し歩いたところに商店街があるのですが,その入り口に作家・林芙美子の像と,彼女の作品『放浪記』の一節が書かれた碑があります。林芙美子は下関生まれの作家で,その後小学校~高校を尾道で過ごしたそうです。

さて,ここには「海が見えた 海が見える」とあります。知り合いの方に教えていただいたのですが,実はこれは改稿されたもので,初出には次のように書かれています。
海が見える。海が見える。五年振りに見る、旅の古里の海!
青空文庫『放浪記(初出)』https://www.aozora.gr.jp/cards/000291/files/45649_26591.html (2025 年 3月 7 日アクセス)
注目したいのは,「見える」を「見えた」に変えている点です。作家であり,恐らく言葉に敏感だったであろう林は,なぜ「見える」を「見えた」に変えたのでしょう。
「~た」は過去ではない
「~た」って何?と聞かれたら,「過去を表す」と答えたくなりますが,実はそうとも言えません。例えば,以下の(1)は,現在のことを述べていますが,「~た」を使っています。これは,何かを発見するときに使うことから「発見のタ」と呼ばれます。
(1)あ、あんなところに財布があった。
では,なぜ発見時に「~た」が使えるのでしょう?それについては,様々な研究者が論じていますが(寺村 1984,尾上 2001,定延 2016など),ここでは定延(2016)の「情報のアクセスポイント」という概念を紹介します。
私たちは,何かを発する際にその情報を頭に浮かべます。脳内の情報にアクセスする際の時間軸のことが,情報のアクセスポイントです。
例えば,先ほどの(1)で「あった」と言えるのは,発見よりも前に「財布はどこだろう」という探索意識があるためです。つまり,「探し始め」という過去の時点に脳内アクセスするから「~た」と発言できる,と考えられます。そのため,下の(2)のように「ある」だと探索意識はなく,偶然発見したという意味になります。

「海が見えた」の意図
ここで話を『放浪記』に戻しましょう。「海が見える」も「海が見えた」も発見を表します。しかし,先述の通り,探索意識がある場合に発見のタを使います。
『放浪記』の一節には,故郷の海を見つけたことへの林の喜びと懐かしさが表現されています。きっと,久々の故郷の海を心待ちにしていたのでしょう。「見える」だと偶然の発見になってしまうので,待ちわびた故郷の海への思いを正確に表すために「見えた」に変更したのではないでしょうか。
そしてその後,今眼前に広がる故郷の海を噛みしめるように「見える」と発しているような,そんな気がします。
ふと,私自身が大事にしている故郷の風景って何かなぁと,そんなことを思いました。